2023年2月9日
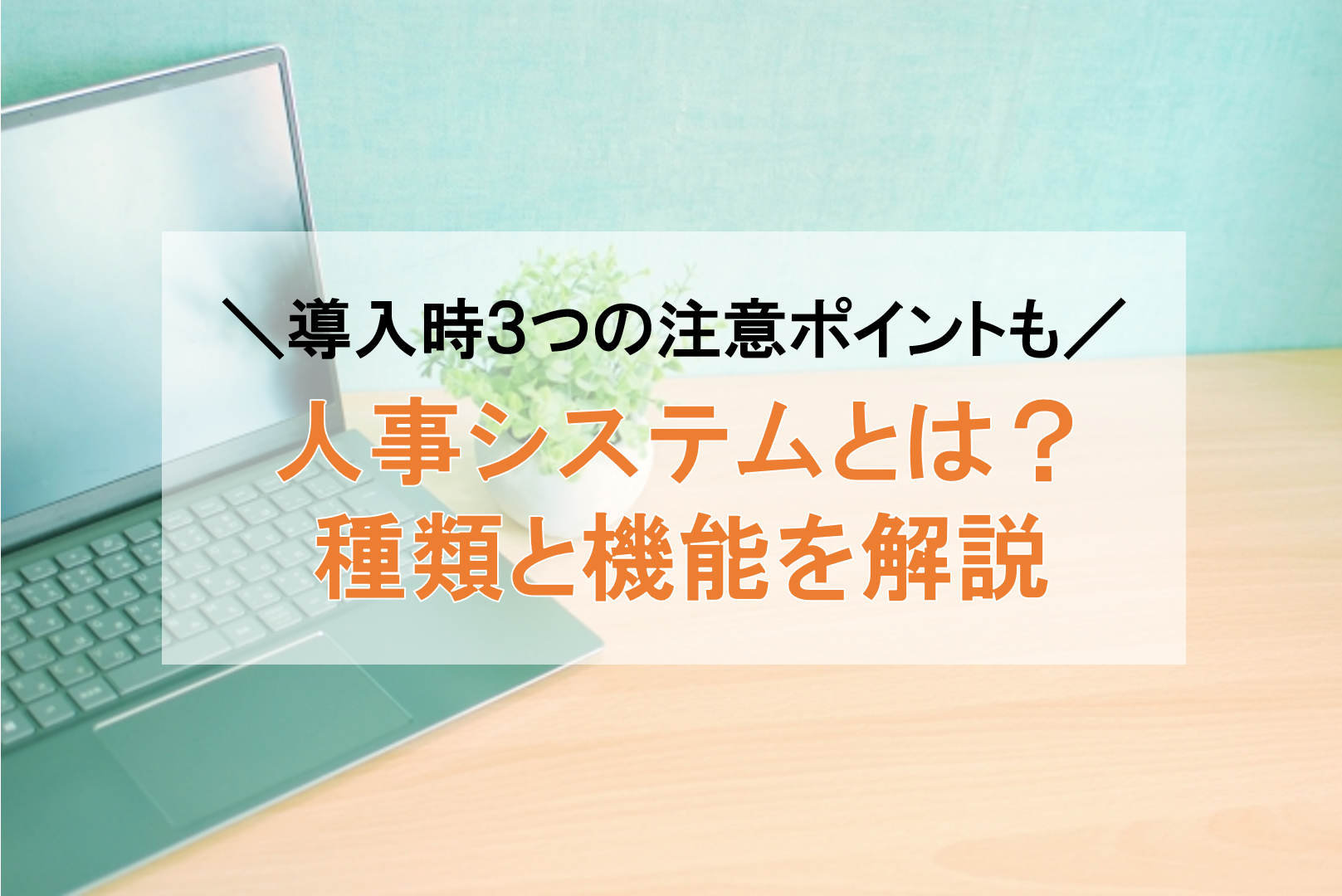
企業の人事業務は、採用、育成、異動・退職、勤怠管理、給与計算、人事評価など、多岐にわたります。
それらの業務を効率化し、人事の業務負担軽減・コスト削減を実現するのが人事システムです。
当記事では、人事システムの基礎知識や種類、導入時に注意すべき3つのポイントをご紹介します。

人事システムとは、従業員に関するデータを一元管理するシステムです。主に人事業務で使用されます。
採用、育成、異動・退職、勤怠管理、給与計算、人事評価など、多岐にわたる人事業務。氏名、性別、住所などの基本情報や配置、処遇、給与計算、社内教育、昇格など従業員に関する情報すべてを一括管理することで、人事業務の効率化を実現します。
冒頭で述べた通り、人事業務は採用・評価・給与計算など多岐にわたります。
そのため、人事システムの機能も幅広く、多様な種類が用意されています。
カバーする業務や機能の違いによって、主に「人事管理」「人材管理」の2種類のシステムに分けられます。

主に労務を担当する人事が使用するシステムです。
従業員の勤怠管理や給与計算、労務管理などの業務をサポートします。
主な機能としては以下のようなものが挙げられます。
従業員の出退勤や休暇などを管理します。
出退勤の打刻情報を集計したり、休暇や残業の申請、直行・直帰、休日出勤、時短勤務など多様な勤務形態に合わせて勤怠状況を管理したりします。給与計算やシフト管理を効率化します。
従業員の給与、社会保険、税金、年金、年末調整などを管理します。勤怠管理機能で集計したデータをもとに、毎月の給与や賞与の計算を行います。
最新の法令に準拠した自動計算も自動計算も可能であり、ヒューマンエラーを防ぎます。

従業員の個人情報や、福利厚生など制度利用に関する申請・手続きを管理します。氏名、住所、所属などの従業員の個人情報を一元的に管理、社会保険・雇用保険などの情報管理や手続きも行います。
2016年に導入されたマイナンバー制度によってさらに高いセキュリティレベルが要求されるようになったことから、管理システムの導入が拡大しています。各申請・手続きの処理も効率化できるため、業務時間を短縮します。

主に採用や人材育成、タレントマネジメントの担当者が使用する機能を集約したシステムです。
従業員のスキルや能力をデータ化・一括管理し、経営に効果的な配置を行うことが可能です。
主な機能として以下のようなものが挙げられます。
応募者の情報や選考状況などを管理、採用活動をスムーズに進めることが可能です。応募者情報や応募経路などの補足情報、日程調整、選考など、複雑かつ多岐にわたる採用活動を効率化します。
新卒採用はもちろん、中途採用やパート・アルバイト、リファラル採用など多様な採用活動に対応するシステムが増加しています。採用活動を起点に、中長期的に経営を支える機能です。

従業員ごとの目標、業績、人事評価などを管理、査定や人材配置に役立つ機能です。
従業員の評価や能力、昇進・入退職など、社内での履歴をまとめて管理することが可能です。
従業員の能力や特性、経験などを管理し、最適な人材配置や育成に活かすためのシステムです。
経験や資格など、従業員の能力を適切に把握することで適切な人材配置を実現します。
ここで人事システムのメリットデメリットについて詳しく知りたい方は下記の記事を参照ください。
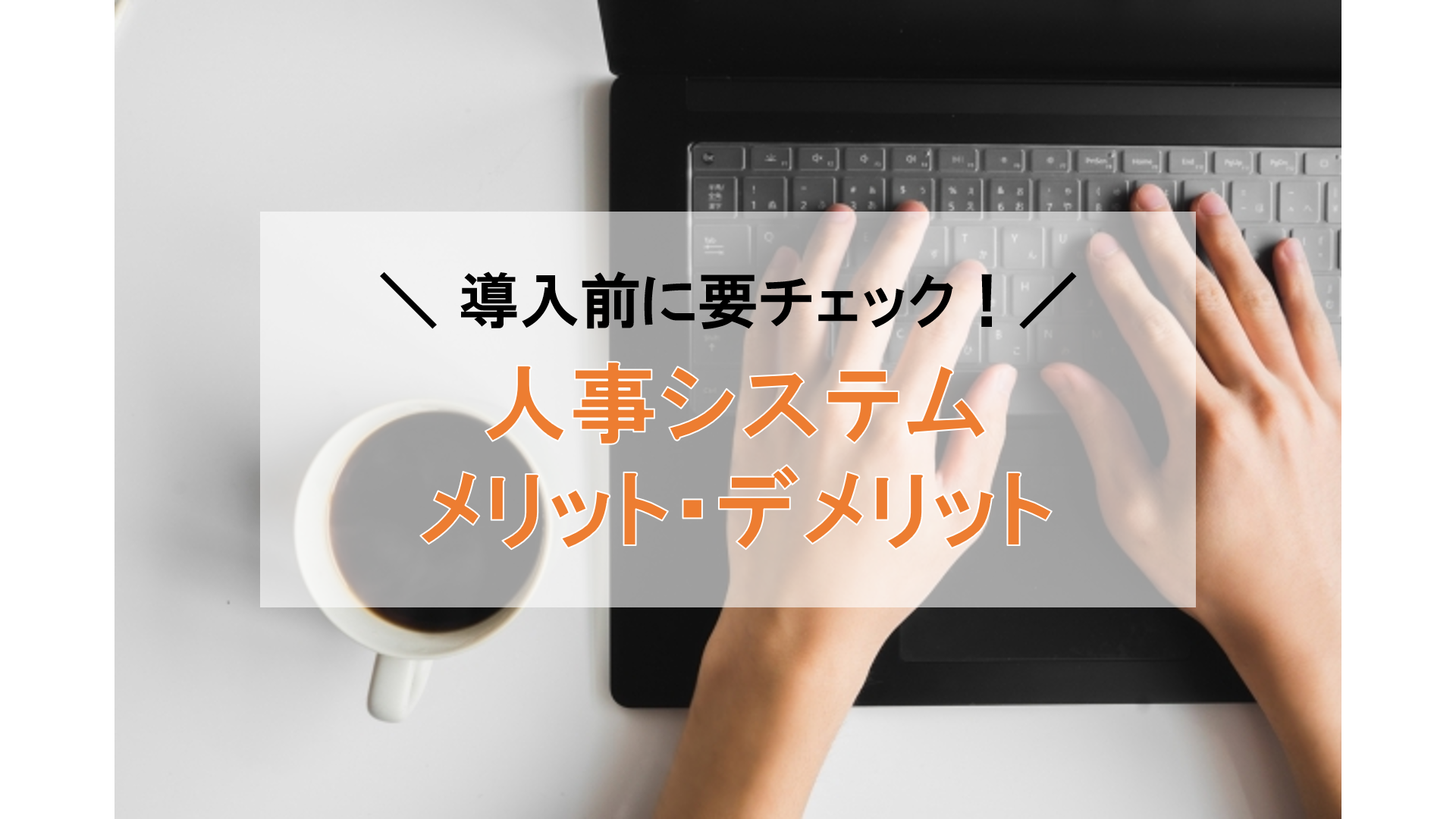
機能がパッケージ化されたシステムを契約する方法です。導入手順や使い方がマニュアル化されており、人事システムの知識に不安があるという方でもスムーズな導入ができます。また、低コストかつ短期間での導入が可能です。
一方で、自社の状況に合わせた機能カスタマイズや他のシステムとの連携は難しいため、導入時にパッケージ内容を入念に確認しておく必要があります。また、導入後にライセンス料などランニングコストがかさむ可能性もあるため、こちらも確認が必要です。

スクラッチ型とは、自社に適したシステムをオーダーメイドで構築する方法です。パッケージ型と比較して、自社独自の業務にも対応できる、自社の業務フローに合わせたシステム設計ができるなどのメリットがあります。
導入時にはコストや構築時間がかかるものの、将来的な機能拡張にも柔軟に対応できるため、長期的に見ればコストを抑えられる方法です。
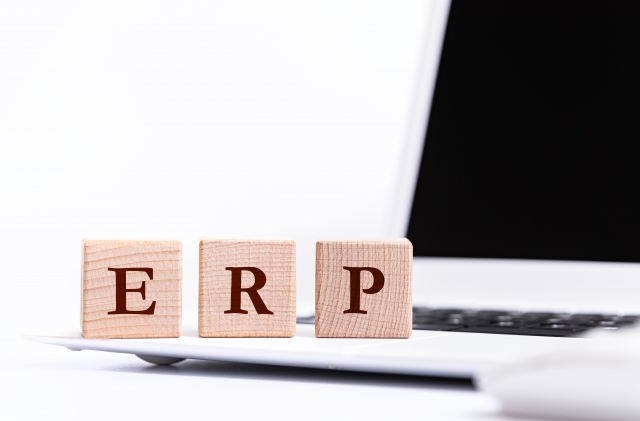
主要な機能のみを備えたパッケージ型のシステムを指します。人事・会計・財務・在庫管理など幅広い機能から、自社に必要な機能のみを選んで使用できる方法です。
既存のパッケージから組み合わせて利用するため、オーダーメイドで構築するスクラッチ型よりも導入時間が短く、パッケージ型よりも柔軟性があるバランスの取れた方法です。
様々なベンダーが提供しているパッケージソフトのなかから、自社に適した機能を持ったものを組み合わせる方法です。
必要な機能・システムを網羅できる反面、システムやデータの連携が困難であるデメリットもあります。
ここで人事システムの導入のポイントについて詳しく知りたい方は下記の記事を参照ください。
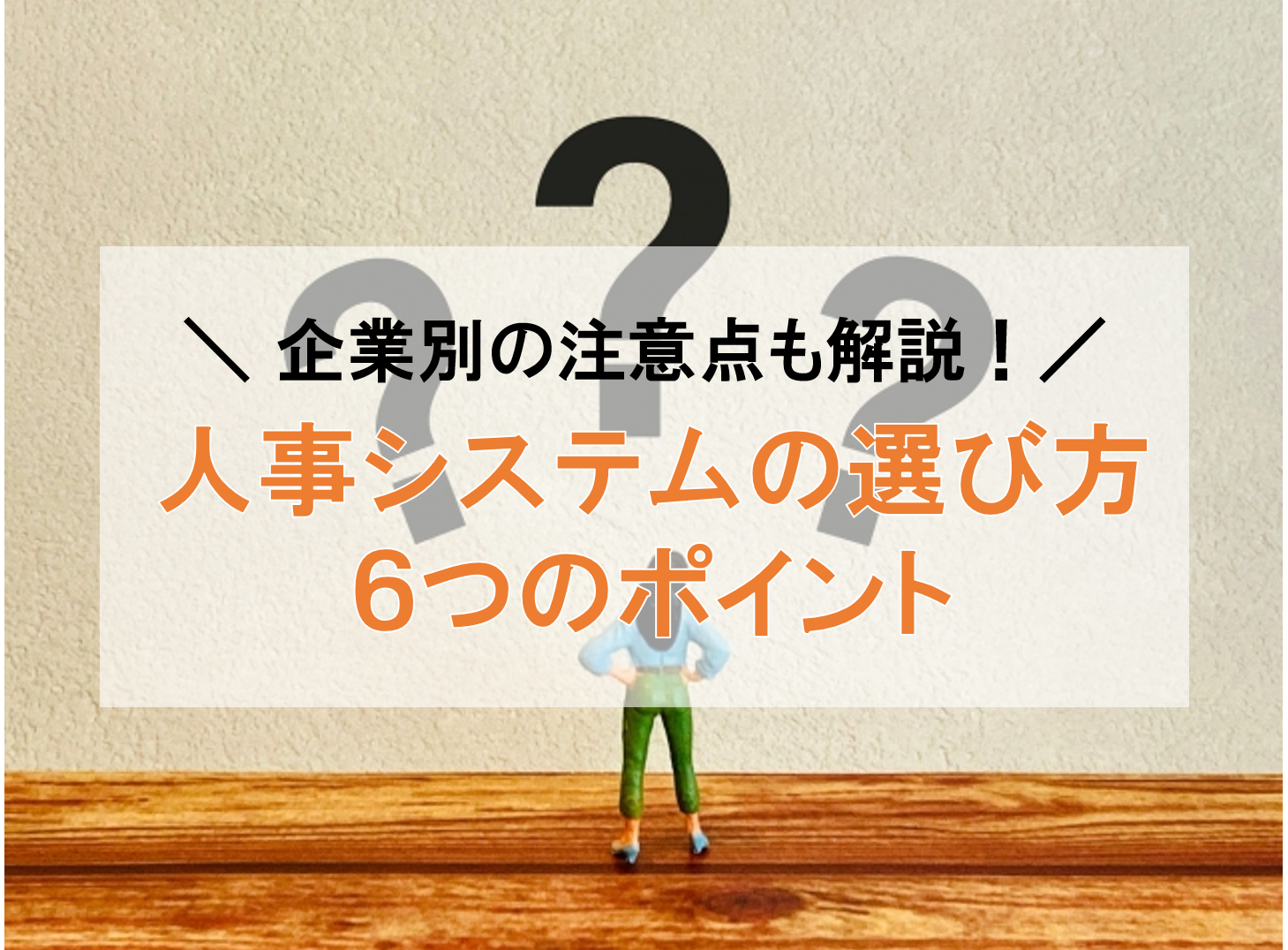

はじめに、何のために人事システムを導入するのか、どのような課題を解決したいのか、導入目的を明確にしましょう。
業務効率化、コスト削減、組織パフォーマンスの向上など、目的の優先順位によってシステムの選定基準が異なります。
人事・総務・労務など業務に携わる従業員から課題を聞き出し、導入目的を共有しておく必要があります。
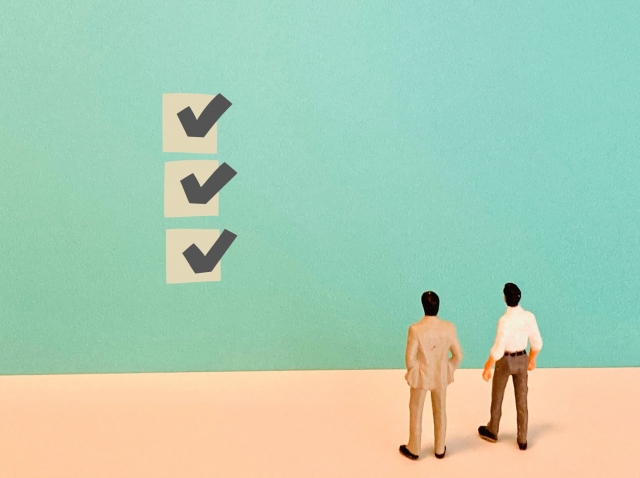
導入目的が定まったら、現在行っている業務の棚卸しを行います。システムを導入すれば目的が達成されるとは限らず、場合によっては自社内の業務フローを変更したり、逆に自社の業務フローに沿った運用ができるシステムを選択したりしなくてはなりません。
また、システム化できる業務・システム化が困難な業務が明らかになり、システム導入による業務効率化・コスト削減の効果を推測することも可能です。
業務の棚卸しによってシステム導入の方針が確定、方針により導入すべきシステムの形態は異なるため、サービスの検討前に業務の棚卸しをする必要があります。
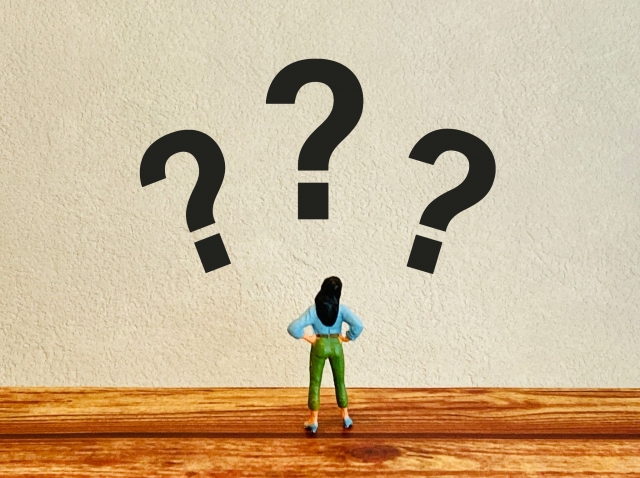
システム選択の方針が定まったら、具体的なサービスの検討に移ります。導入目的・導入したいシステムの形態や機能、料金プラン、セキュリティ、サポート体制など、自社に合ったシステムを比較検討しましょう。
特に、システムの使いやすさは導入後の普及に不可欠ですが、説明だけでは分からない部分も多くあります。無料体験やデモで実際に体感してみる必要があります。

導入するシステムが決定したら、実際の契約やデータ移管に移ります。現在利用しているシステムや紙媒体の資料から、新たなシステムにデータを移管します。
企業の規模や年数によるものの、この導入作業には膨大な時間がかかります。長い場合には数か月を要する場合もあるため、余裕を持った導入スケジュールを立てておくことが重要です。

移行作業が完了したら、新たなシステムの運用を開始できます。人事・総務・労務担当者へ目的・新しい業務フロー・使い方などを共有することはもちろん、一般の従業員に対しても新システム導入・システム移行に関して情報を共有する必要があります。
特に従業員からの申請をシステムで行う形式に移行する場合には、従業員の理解と協力が不可欠です。事前に入念な情報共有を行い、混乱を最小限に抑えられるような移行を行いましょう。

2016年にマイナンバー制度が開始されてから、企業にはより厳重な個人情報の保護が課されることになりました。その影響から人事システムを導入する企業も増加しましたが、システムを導入したからといって情報漏えいのリスクを0にすることはできません。
自社が求めるセキュリティレベルを備えたシステムであるかを確認しましょう。情報漏えいを防止するための社内規定を新たに作成することもおすすめです。

人事システムの導入方法により、導入時・導入後にかかる費用は大きく異なります。初期費用・月額費用の有無やその価格、将来的に法改正やカスタマイズに伴いかかる費用はどれくらいなのかを比較する必要があります。
初期費用無料など、様々なキャンペーンがありますが、長い目で見たときに自社に最も適したシステムはどれなのか検討しましょう。

人事システムを単体で利用するケースは少なく、企業それぞれが利用している勤怠管理システムや給与計算システムなど、各システムのデータを連携させることでより業務の効率化を実現します。
現在使用しているシステムとの連携は可能か、自社内で完結できるような方法でスムーズに連携できるかを確認しておきましょう。
ここで、企業の特徴ごとにおすすめする18の人事システムについて。詳しく知りたい方は下記の記事を参照ください。
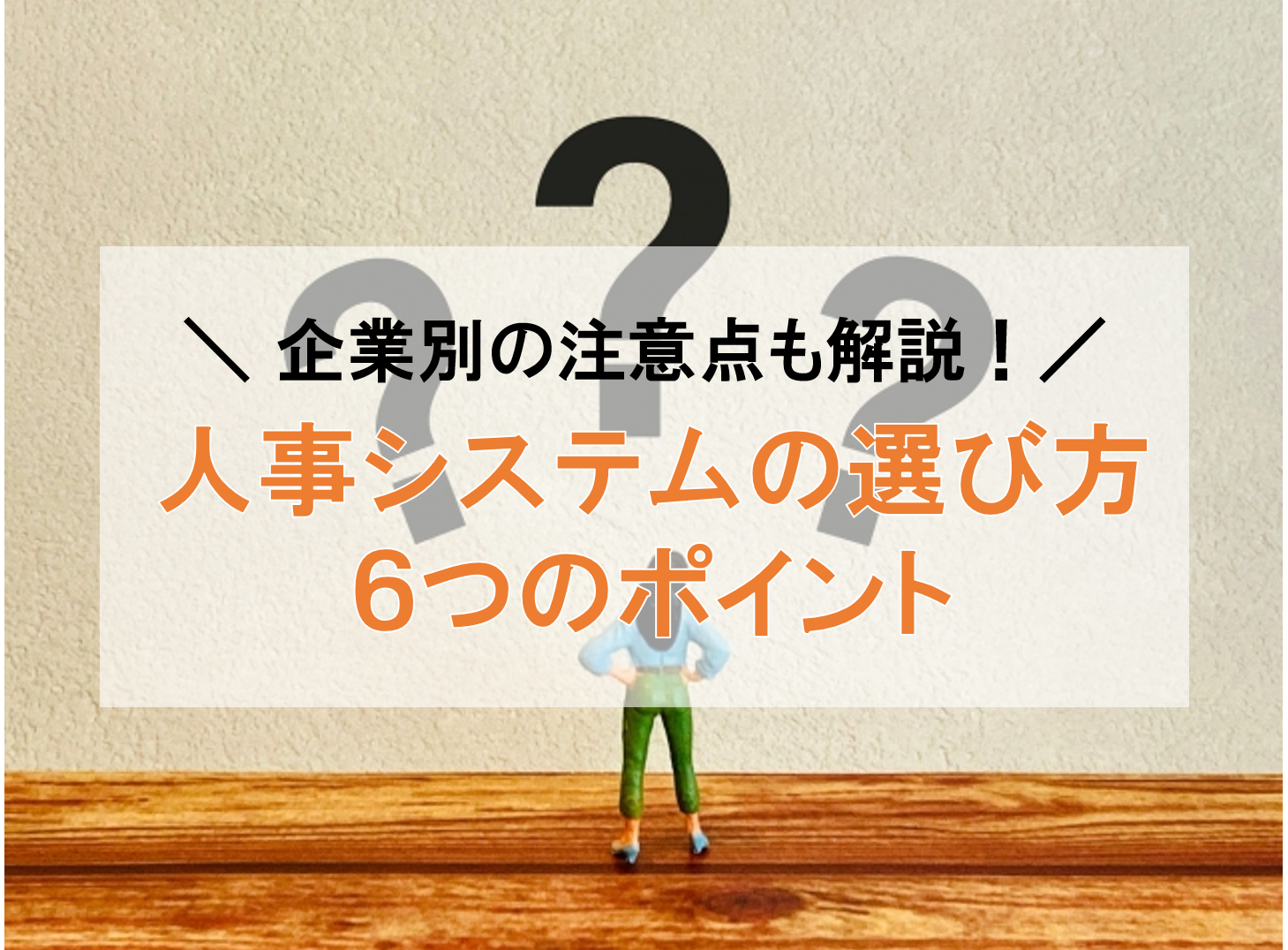
最後に当社では、採用から退職、社労士への手続きも自動化する労務管理システム「MOT/HG」を提供しています。
1ID 170円~(月8,500円/50ID)利用できる業界最安の労務管理システムです。
価格が手ごろということだけでなく、コミュニケーションツールとして、クラウド電話も利用できるので、03などの外線受発信やチャットなどの利用が可能です。
人事や総務の業務だけでなく電話業務もDX化する「MOT/HG」を是非、ご利用してみてください。