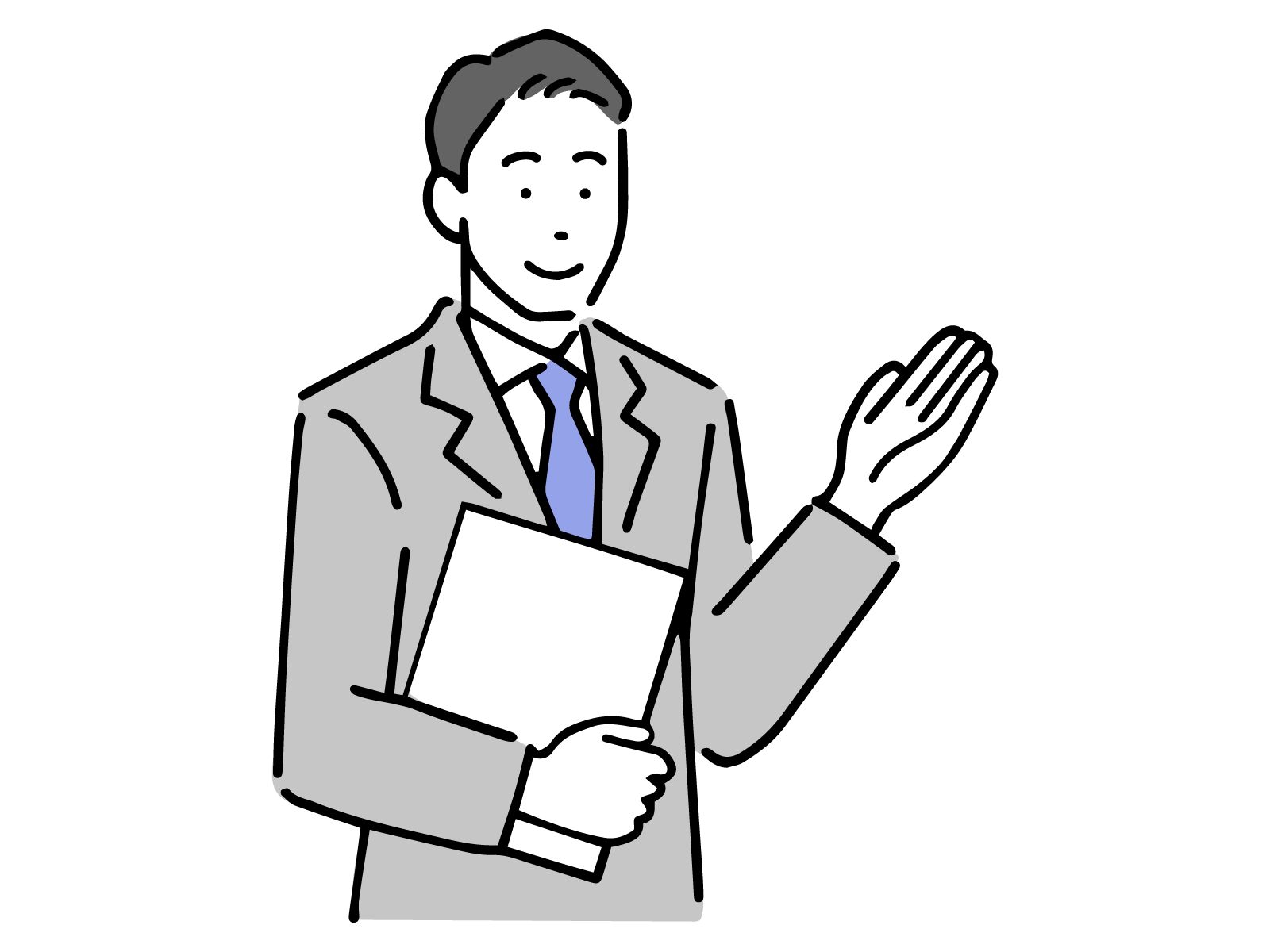2025年9月22日

建設現場で注目を集めている「遠隔臨場」。
国土交通省も推進しており、移動せずに現場の状況を確認できるため、働き方改革・コスト削減・人材不足解消に効果的です。
とはいえ、
「遠隔臨場ってそもそも何?」
「どんな機材が必要?」
「ガイドラインはどうなってる?」
と疑問を持つ方も多いはず。
本記事では、遠隔臨場の基礎知識から、国交省ガイドライン、必要な通信環境と機材、おすすめのウェアラブルカメラまでをわかりやすく解説します。
これから遠隔臨場を始めたい現場監督・施工管理者の方はぜひ参考にしてください。
遠隔臨場とは、建設現場の立会いや検査、確認作業を現場に行かずにオンラインで行える仕組みのことです。
現場に設置したカメラや、作業員が装着したウェアラブルカメラを通じて、映像と音声をリアルタイムで配信し、遠隔地にいる監督や発注者が確認できます。
目的は、現場の移動時間・人件費を削減しながら、品質管理や安全管理を確保することです。
また、立会検査や中間検査の記録をデジタルデータとして残せるため、後日の証拠保全やトレーサビリティ強化にもつながります。

国土交通省は、建設業界の人手不足・長時間労働・移動コストといった課題解決のため、遠隔臨場の活用を推奨しています。
特に「建設現場の生産性向上(i-Construction)」の一環として、2020年以降、遠隔臨場のガイドラインを整備し、オンラインによる立会検査や出来形確認を可能にしました。
これにより、発注者・監督職員が現場に出向く回数を減らしつつ、現場の品質・安全を維持する「建設現場DX」が進められています。
今後は、国交省案件だけでなく民間工事でも遠隔臨場の活用が広がると見込まれています。
遠隔臨場の最大のメリットは、現場に行かなくても立会や検査ができることです。
監督や施工管理者は、現場ごとに移動する必要がなくなり、移動時間・交通費・残業時間の大幅削減が可能になります。
結果として、1日のスケジュールに余裕が生まれ、複数現場を効率的に管理できるようになり、働き方改革や人手不足対策にも貢献します。
発注者や元請けにとっても、遠隔臨場は大きなメリットがあります。
現場に足を運ばなくても、リアルタイムで作業状況を確認できるため、迅速な意思決定が可能になります。
さらに、撮影した映像はそのまま記録として保存できるため、検査履歴や証拠として活用でき、品質保証やクレーム対応の強化にもつながります。
一方で、遠隔臨場にはいくつかの注意点もあります。
まず、通信環境が不安定だと映像や音声が途切れやすいため、モバイル回線やWi-Fiの整備が必要です。
また、カメラや通信機材の初期投資や運用コストが発生します。
さらに、現場スタッフがカメラを装着して撮影するため、操作方法や撮影ルールの教育が不可欠です。
これらの課題は、安定した通信と高性能なウェアラブルカメラを選ぶことで解決しやすくなります。
国土交通省は2020年以降、建設現場の生産性向上を目的として遠隔臨場のガイドラインを整備しています。
この指針では、立会検査や出来形確認を現場に行かずに行うことを認めるとともに、映像と音声がリアルタイムで確認できること、記録として残せることを求めています。
また、現場の作業員や監督職員が使いやすい機材であること、通信トラブル時の対応フローを定めることも推奨されています。
ガイドラインでは、映像と音声の品質について以下の要件が推奨されています。
・通信回線速度: 下り最大50Mbps以上、上り最大5Mbps以上が目安
・転送レート: 映像と音声の平均転送レートとして、1Mbps以上
・カメラ画質:画素数:640×480 以上
・フレームレート:15fps 以上
・音声:マイク・スピーカー モノラル(1 チャンネル)以上
特に建設現場では騒音が多いため、ノイズキャンセリング機能を搭載した高性能イヤホンマイクや骨伝導イヤホンの活用が推奨されます。
遠隔臨場で取得した映像や音声は、後日確認できるように保存することが求められます。
国交省では明確な保存期間を定めていませんが、多くの発注者は検査記録や竣工書類と同等に保管する運用を行っています。
保存形式はクラウドストレージや社内サーバーなどが利用され、改ざん防止とアクセス管理も重要です。
このため、遠隔臨場システムを選ぶ際は、自動録画機能やデータ管理機能があるものを選ぶと安心です。
遠隔臨場を成功させるには、国交省のガイドラインに沿った機材を揃えることが第一歩です。
ただし、現場では機材が多いと作業の妨げになるため、必要最小限でシンプルな構成を目指しましょう。以下のポイントを押さえれば、無駄なく準備できます。
遠隔臨場の中心となるのがハンズフリーで映像を共有できるカメラです。
・ウェアラブルカメラ:胸部やヘルメットに装着し、作業者の目線で映像をリアルタイム共有。防水・防塵性能(IP65以上)があれば屋外でも安心です。SIM内蔵モデルなら、別途通信機器を持つ必要もありません。
・スマートグラス:作業者の視線そのままを配信でき、監督者は現場にいる感覚で指示可能。マイク付きならハンズフリー通話にも対応します。
映像や音声を安定して送るには通信環境が重要です。
通信機能付きカメラがあれば追加機材は不要ですが、そうでない場合は以下を準備します
・モバイルルーター:Wi-Fi環境がない現場で高速通信を確保。複数人接続や高画質配信なら5G対応モデルが最適。
・スマホ・タブレット:映像確認やチャット指示用に便利。SIMフリー端末を選び、現場の電波状況に合わせてキャリアを選定しましょう。
長時間の検査や複数人での視聴には、補助機材があると便利です。
・三脚・スタンド:特定の場所を固定撮影するときに使用。両手が空き作業効率が上がります。
・モバイルバッテリー:屋外では必須。カメラ・スマホ・ルーターを同時充電できる大容量タイプがおすすめ。
・ヘッドセット・マイク:騒音が多い現場ではノイズキャンセリング付きマイクでクリアな音声を確保しましょう。
遠隔臨場では「安定した映像・音声を届けること」が何より重要です。ここでは、VALTECのウェアラブルカメラをはじめ、代表的な機材と選び方のポイントを解説します。

VALTECのウェアラブルカメラは、建設現場やインフラ点検の遠隔臨場向けに設計された防水・防塵仕様(IP68)のカメラです。
・高画質フルHD映像をリアルタイムで共有可能
・IP電話メーカーがソフト開発したウェアラブルカメラ
・インカム機能搭載で、ボタンを押すだけでグループ通話開始
・LTE/5G通信対応ルーターと連携して安定配信
VALTECではデモ機貸し出しや初期設定サポートも行っており、初めての遠隔臨場導入でも安心です。
市場には様々な遠隔臨場対応カメラがあります。
・スマートグラス型(RealWear、Vuzix など):視線映像を送れるため、細かい作業指示に向いています
・アクションカメラ型(GoPro など):軽量・高画質でコストを抑えて導入可能
・360度カメラ:現場全体を一度に記録でき、複数視点を切り替え可能
用途や予算、通信環境に合わせて選定しましょう。
遠隔臨場用カメラを選ぶ際は、以下のポイントを押さえると失敗しません。
・防水・防塵性能:屋外利用ならIP65以上が目安
・画質:フルHD(1920×1080)以上、広角レンズが理想
・通話機能:通話品質がよいものを選定、複数人対応する場合インカム機能は必須
・通信方式:Wi-FiだけでなくLTE/5G通信に対応しているか
・バッテリー駆動時間:2〜4時間以上持続するモデルがおすすめ
これらを満たすカメラを選べば、国交省の遠隔臨場ガイドラインにも適合しやすく、スムーズに導入できます。
遠隔臨場は、国交省が推進する建設現場DXの重要な取り組みであり、移動コスト削減や現場の効率化に大きく貢献します。
導入する際は、通信環境・カメラ・補助機材を整備することが成功のポイントです。
特に、防水・防塵対応のウェアラブルカメラや安定した通信機器の選定は、遠隔臨場の品質を左右します。 VALTECでは、建設・インフラ現場向けに最適化したウェアラブルカメラと通信ソリューションを提供しており、 初めての導入でもスムーズに運用できるよう、デモ機貸し出し・導入支援・サポート体制を整えています。